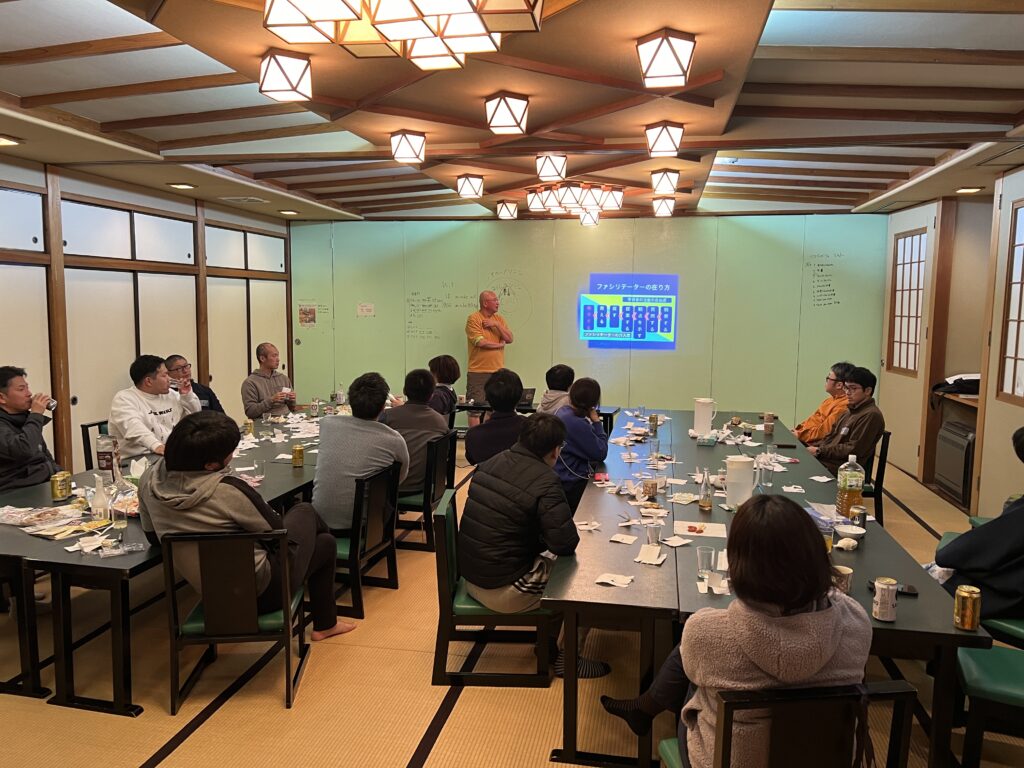この1週間にまるまる3日、LAFTの研修をつめこんだ。その甲斐あってか、井本さん、KAIさん、それぞれの教育スペシャリスト2人に共通するものがみてとれた。僕はこれこそが自分のマインドを変える、決め手だと思ったものがあった。
「アクティビティそのものはプロジェクト・アドベンチャーではなく、考え方そのものである。」
そこから、プロジェクト・アドベンチャーは体験学習のサイクルを学ぶひとつのツールということが伝わってくる。だからこそ、日常の生活、日々の教科指導、連れションにいたってまで、すべてにわたってプロジェクト・アドベンチャーであり、体験学習なのである。至言なり。
KAI実践のスタートは、そこにいる人達のCゾーン(安心ゾーン)をつくることから始まる。学年最初の学級づくりは、凝集性高めであるのは、この安心できる居心地の良い場づくりのためだ。そのCゾーンづくりに向けて「温める」「(お互いを)知っている」「群れて遊ぶ」「勝ち負け概念を崩す」「失敗のはずかしさをとる」など、プロジェクト・アドベンチャーを通して体験的に、学んでいく。頭でわかったことなんて、体験に比べたら足下にも及ばないからだ。
そこから、少しずつアドベンチャー色が高まるイニシアティブ(課題解決のアクティビティ)が始まる。子どもたち同士が本音でぶつかるストーミング(対立)が起こることで、その集団、学級は少しずつ成長していく。
と、ここまでが一学期であって、二学期以降はアクティビティをやらない。そこでこう問われた。
「パイプライン(パイプをつなげて玉をゴールに運ぶアクティビティ)では子どもたちは協力できても、日頃の掃除の場面ではぜんぜん協力しないのはなぜ?」
そこで、日常における、アドベンチャーの必要性が問われる。日常の何気ない活動にアドベンチャー、つまりは自分たちで何かを変えようとトライアンドエラーしながら体験的に学ぼうとできる「体験学習のサイクル」がそこにあるかどうかで、プロジェクト・アドベンチャーでの学びを活かせるのか、その場限りの体験となるのか、分かれ目となる。学んだことを、よりオーセンティックに実際に活かせるすべて場でホールデザインしているのがKAI実践の真骨頂でもある。
(体験学習のサイクルを学んだのなら、その)ならったことをつかおうよ。あたりまえといっちゃ、あたりまえなのだが、僕らはどうして「この活動はこれ」「あの学習はあの学習」と分断して捉えてしまうのだろうか? これは学校教育もっている構造の問題でもありそうだ。そして、そこからどうしたら解脱できるのだろうか。
KAIの公立校実践では、お掃除ボランティア、教室リフォーム、そして給食準備もしかり、日常全てがアドベンチャーとなっていく。さらには、国語、算数、理科、社会、全てがアドベンチャーになるように、子どもたちの挑戦できる設計をしていく。学校生活「全て」がアドベンチャーに変わっていく。
KAI曰く
「社会科見学は一番アドベンチャーに変えやすい! 現地集合、現地解散とかな。他の学校が先生に連れられて集団行動しているけど、うちの学校は藪の中から『たどりついたー!』と方々から集まってくる。がはは。おもしろいでしょー」
ここで、だれもがこう思うはずだ。
「そこまでやれるのだろうか」
「とはいうものの。。。」
「だって〜、保護者が」
「もう学年の先生とは、管理職とはうまくやれないのではないか」
など、様々な不安がよぎる。そこで、KAIに直接、その場できいてみた。
KAIらしいつきぬけた実践をするためには、どんな心構えが必要なのか、どうしたら、「解脱」できるのか?
すると、KAIは
「誰がその姿(いまやっている活動で学び取る姿)を望んでいるのか? 子どもは本当にその姿を願っているのか? 保護者もか? 例えば、休み時間は全員外遊びに外へ行かせることとか、教師自身は本当に望んでいないけど、これって本当に辛くない?」
とことん、子ども中心、学習者中心である。この全てに通底する信念があってこそのKAI実践だ。最後に勇気をもらう言葉をもらう。
「アドベンチャーを学校教育の中でやっていると、『これからの教育はこういうことが必要ですよね』と保護者は言ってくれる。子どもや保護者に理解してもらってきた。子どもの姿が変われば、少しずつ親の姿や管理職も変わってくる。だから、先生自身がアドベンチャーすること。最後に、あとは先生の覚悟次第。アドベンチャーを子どもは大歓迎してくれるよ」
すべてにおいて、KAIの目にはゴールに子どもの姿が映っている。そこには忖度やおつきあいは存在しないのかもしれない。貫ける信念、あり方がぶれないこと。これは覚悟の問題だ。これは先日のLAFTで井本さんも言葉は違うが、同じ姿勢、同じ実践をみせてくれ、2人に共通するものだ。
子どもにとって、どれだけ本気になれるかだ。心を奮い立たせられ、揺さぶられる。